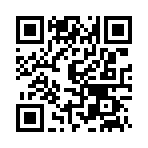2015年01月21日
大寒といえば・・・干物??
昨日は大寒で、本来一年を通じて最も寒いとされる日でしたが、実際はここのところ暫く寒さは緩んでいる感じですね。
実際は小寒から立春までの間あたりが一年で最も寒い時期のようですが、週間天気予報が出ている期間も予想最高気温が10度前後となっていますし、寒波の来ぬ間に海づり公園に釣行を!

月曜日の須磨の釣果情報を見てみると、シラサエビを使ったウキ流し釣りで良型のマダイが釣れています。
他にはメバル・ガシラ・アブラメといった根魚御三家や、ウミタナゴも。
特にウミタナゴは数多く釣れているので、これに狙いを絞ってみるのも一興かと。
さて、この海タナゴを調理したことがある方はご存知でしょうが、身が柔らかいので塩焼きにすると焼き網に張り付き、慌ててひっくり返そうとすると見るも無残にボロボロに・・・ということになります。
ウミタナゴを食べるには、この柔らかい身を、いかに締めるかというのがポイントになります。
ひとつの食べ方としては、じっくりと素焼きで焼き上げ、一度冷ますと身が締まるので、この冷ましたものを煮付けるという方法があります。
一度焼いて冷ますことで身が崩れにくく、味も濃くなるので煮付け好きにはおススメ。
そして、個人的に一押しの調理法は干物。
以下に調理法を。
まず、ウロコを丁寧に剥がします。
炙って適度に焦げ目の入った皮は美味ですので、綺麗にウロコを取りましょう。
開く際に邪魔になりますので、背ビレ、腹ビレの周りは特に念入りに・・・(写真①、②)

見栄え良く頭を残すなら、背中側から包丁を入れて腹側がつながった状態になる『背開き』にします。(写真③、④)

形にこだわりがなければ、頭を落とし(写真⑤)腹側から包丁を入れて、『腹開き』(写真⑥、⑦)にします。
このあたりは、やり易いようにお好みで。


開き終わったら、洗ってキッチンペーパーで水分をよく拭き取り、ザルに並べます。(写真⑧)
 塩焼きよりもやや多めの塩を振り、(写真⑨)風通しの良い所で陰干しにします。
塩焼きよりもやや多めの塩を振り、(写真⑨)風通しの良い所で陰干しにします。
この季節、寒風吹きすさぶ日は特に干物日和。
1時間ほどで、身から水分がにじみ出てきます(写真⑩)ので、再びキッチンペーパーで水分をふき取ります。(写真⑪)

条件にもよりますが、干し始めて3時間ほどで表面が乾き始め(写真⑫)5~6時間で半乾の干物の完成(写真⑬、⑭)です。

*以上、写真は以前のメルマガから使用しています。
更に一晩干しても美味しくいただけますので、干し加減はお好みに合わせて。
これを焼き目が付く程度に焼き上げ、レモンや柚子などの柑橘類を搾って、数滴の醤油をたらせば、あとはおかずにでも、酒の肴にでも。
可能な方は、七輪の炭で焼くことをお勧めします。
炭火で焼いた魚の味は、ガスで焼いたものとは一味違いますからね。
新鮮な魚を食べ慣れた常連のお客様を、何人も唸らせた一品・・・いや逸品ですから、これだけの手間をかけるだけの価値は間違いなくあります!
ちなみに、今釣れる魚なら、メバルの干物も意外な旨さですので、どうぞこちらもお験しください。
方法は、海タナゴと同様ですが、こちらはもともと身が締まった魚ですので、干し過ぎには要注意。
きっと今まで「なんだ、ウミタナゴかぁ・・・」なんて思っていらした方も多いと思いますが食べてみる価値ありますよ。
武道では、寒さの厳しい大寒あたりに寒稽古が行われます。
ここはひとつ釣り師も寒さに負けず、防寒グッズと調理グッズを忘れずに、干物の材料を釣りに海づり公園に寒稽古に行きませんか。
実際は小寒から立春までの間あたりが一年で最も寒い時期のようですが、週間天気予報が出ている期間も予想最高気温が10度前後となっていますし、寒波の来ぬ間に海づり公園に釣行を!
月曜日の須磨の釣果情報を見てみると、シラサエビを使ったウキ流し釣りで良型のマダイが釣れています。
他にはメバル・ガシラ・アブラメといった根魚御三家や、ウミタナゴも。
特にウミタナゴは数多く釣れているので、これに狙いを絞ってみるのも一興かと。
さて、この海タナゴを調理したことがある方はご存知でしょうが、身が柔らかいので塩焼きにすると焼き網に張り付き、慌ててひっくり返そうとすると見るも無残にボロボロに・・・ということになります。
ウミタナゴを食べるには、この柔らかい身を、いかに締めるかというのがポイントになります。
ひとつの食べ方としては、じっくりと素焼きで焼き上げ、一度冷ますと身が締まるので、この冷ましたものを煮付けるという方法があります。
一度焼いて冷ますことで身が崩れにくく、味も濃くなるので煮付け好きにはおススメ。
そして、個人的に一押しの調理法は干物。
以下に調理法を。
まず、ウロコを丁寧に剥がします。
炙って適度に焦げ目の入った皮は美味ですので、綺麗にウロコを取りましょう。
開く際に邪魔になりますので、背ビレ、腹ビレの周りは特に念入りに・・・(写真①、②)

見栄え良く頭を残すなら、背中側から包丁を入れて腹側がつながった状態になる『背開き』にします。(写真③、④)


形にこだわりがなければ、頭を落とし(写真⑤)腹側から包丁を入れて、『腹開き』(写真⑥、⑦)にします。
このあたりは、やり易いようにお好みで。


開き終わったら、洗ってキッチンペーパーで水分をよく拭き取り、ザルに並べます。(写真⑧)
 塩焼きよりもやや多めの塩を振り、(写真⑨)風通しの良い所で陰干しにします。
塩焼きよりもやや多めの塩を振り、(写真⑨)風通しの良い所で陰干しにします。この季節、寒風吹きすさぶ日は特に干物日和。
1時間ほどで、身から水分がにじみ出てきます(写真⑩)ので、再びキッチンペーパーで水分をふき取ります。(写真⑪)

条件にもよりますが、干し始めて3時間ほどで表面が乾き始め(写真⑫)5~6時間で半乾の干物の完成(写真⑬、⑭)です。

*以上、写真は以前のメルマガから使用しています。
更に一晩干しても美味しくいただけますので、干し加減はお好みに合わせて。
これを焼き目が付く程度に焼き上げ、レモンや柚子などの柑橘類を搾って、数滴の醤油をたらせば、あとはおかずにでも、酒の肴にでも。
可能な方は、七輪の炭で焼くことをお勧めします。
炭火で焼いた魚の味は、ガスで焼いたものとは一味違いますからね。
新鮮な魚を食べ慣れた常連のお客様を、何人も唸らせた一品・・・いや逸品ですから、これだけの手間をかけるだけの価値は間違いなくあります!
ちなみに、今釣れる魚なら、メバルの干物も意外な旨さですので、どうぞこちらもお験しください。
方法は、海タナゴと同様ですが、こちらはもともと身が締まった魚ですので、干し過ぎには要注意。
きっと今まで「なんだ、ウミタナゴかぁ・・・」なんて思っていらした方も多いと思いますが食べてみる価値ありますよ。
武道では、寒さの厳しい大寒あたりに寒稽古が行われます。
ここはひとつ釣り師も寒さに負けず、防寒グッズと調理グッズを忘れずに、干物の材料を釣りに海づり公園に寒稽古に行きませんか。
Posted by 海づり公園スタッフブログ at 08:57
│雑談(須磨)